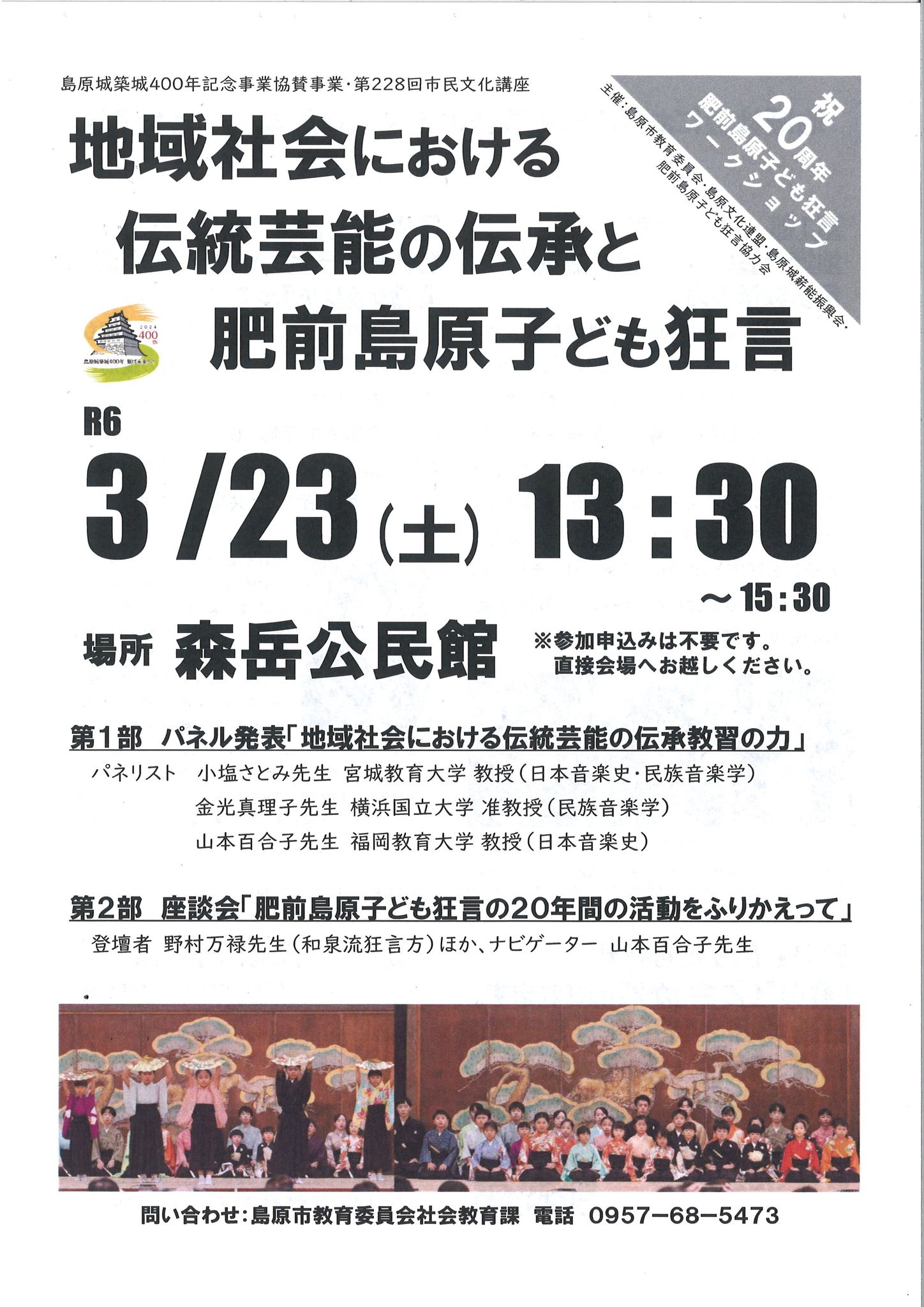1、能とはどんなもの?
能は日本が世界に誇る伝統芸能です。600年も昔に出来ました。西洋演劇のもととなったシェ―クスピア劇よりも200年も古いのです。
能は演劇で、舞踏と音楽と演劇が一体となった総合芸術です。狂言はその中の一つです。もっと能・狂言について知りたい方へお話ししましょう。
さて、能の舞台はどのように進行するのでしょうか。
能のドラマは、謡(ウタイ・声楽)によって進行します。謡は立ち方(登場人物)と地謡(斉唱団)が受け持ちます。
曲の最初は、立ち方のコトバという謡で始まります。やがて音楽的な謡へ移り、最後は力強い地謡で終わります。
舞台後方に並ぶ笛、小鼓(つづみ)、大鼓(かわ)、太鼓(たいこ)の囃子(はやし)が次第に謡と重なって、ともに明確なリズムを刻みます。それと共に舞(ダンスシーン)が続きます。ミュージカルでよく使われる手法が、すでに数百年も昔から用いられていたのです。抽象的な舞を一曲、クライマックスで舞うのも能の特徴です。
シテ(主役)は面(おもて・仮面)を用いる場合が多いのです。本説(ホンゼツ・典拠)を古典に求めていることも多いなど、能はかなり特殊な演劇です。
まとめてみると・・・
「能」は (1) 音楽劇です。謡という声楽と、笛、鼓、大鼓、太鼓という器楽演奏があります。これらがシテと渡り合って能を作り上げます。
(2) 化面劇です。しかし能面は仮面ではありません。能面こそが真実の顔といわれ、再現実写の演劇ではないのです。
(3) もうひとつの特徴は、狂言というパートナーを必要とすることです。